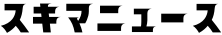「升(ます)で日本酒を飲む」というと、特別な場や居酒屋の演出を思い浮かべる方も多いかもしれません。実は、升酒には長い歴史と、独特の楽しみ方があります。本記事では、升の種類や使い方、もっきりと呼ばれる提供スタイルまでを分かりやすく解説します。自宅でも気軽に升酒を楽しむ方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
升とは?日本酒と升の関係
升のサイズと一合の意味
升(ます)は、本来は体積を量る「計量器」として使われてきた道具です。特に米や豆などの穀物の計量に使われることが多く、江戸時代には年貢の納付や市場での取引にも使われていました。公的な標準器として扱われていた歴史があり、日本の生活文化に深く根付いた道具です。
日本酒の世界では、1合(約180ml)を正確に量れる器として親しまれており、「一合升(いちごうます)」と呼ばれる木製の升が一般的です。この単位が日本酒の計量の基礎にもなっています。升酒で提供される量はこの1合が基本で、升そのものが「1合をぴったり注げる容器」として使われているのです。
なお、「一升瓶」は1.8L=10合を指す容量の単位ですが、「升(ます)」という道具そのものが一升分の大きさであるわけではありません。飲用に使われるのは一合升(いちごうます)で、容量は約180mlです。このように「升」は、単位と器の両方を表す言葉として使われています。
祝い事と升酒の文化的背景
日本では、古くから祝い事や儀式の場で升が使われてきました。特に結婚式や新年などでは、升に注いだ日本酒で「乾杯」を行い、幸運や繁栄を願います。これは升が「増す(ます)=繁栄する・幸せが増える」という言葉とつながる縁起物とされてきたためです。
こうした背景から、升酒は単なる飲み方ではなく、「意味を込めて飲む」日本酒のスタイルとして根付いています。
升を使った日本酒の飲み方
升の持ち方・飲み方
升に直接注がれた酒を飲むときは、升の角を両手でそっと持ち、角のひとつから口をつけて静かに飲むのが一般的です。四隅のうちどこから飲むかに厳密な決まりはありませんが、斜めに持って飲むとこぼれにくく、安定します。香りを立たせたいときは、息を吸い込むようにゆっくりと口に運ぶのがコツです。
グラスを升にのせる(“もっきり”スタイル)
もっきりとは、グラスを升の中に置いて、日本酒をこぼれるまでたっぷり注ぐ提供スタイルのこと。升にも酒があふれることで「サービス精神」や「おもてなしの気持ち」を表します。升に溜まった酒をあとからグラスに移すなどして、最後までしっかり楽しめるのも魅力です。
自宅で升酒を楽しむために
升の種類と商品例
ガラス製やプラスチック製(樹脂製)の升も一部で存在しますが、木製を避けたい場合は、升ではなく猪口やぐい呑み、グラスなど他の器を選ぶのが一般的です。
升のメンテナンス方法
木製の升は水分を吸いやすいため、使用後はすぐにぬるま湯で洗い、柔らかい布で水気を拭き取って陰干しするのが基本です。洗剤は香りが残ることがあるため、使用は控えめにするとよいでしょう。食洗機や電子レンジの使用は避けてください。
一方、塗り升は表面がコーティングされているため、木製よりも水を吸いにくく、汚れも落としやすいのが特徴です。使用後は柔らかいスポンジで優しく洗い、同様に陰干しすれば十分です。—
まとめ|升で日本酒を飲む魅力を日常に
升で飲む日本酒には、単なる器を超えた文化的な意味と、五感を使って味わう楽しみがあります。特別な場面だけでなく、家庭でも気軽に取り入れることで、日本酒の時間がより豊かになるはずです。木の香りとともに、一合をゆっくり味わうだけでも、日本酒の楽しみ方が広がります。